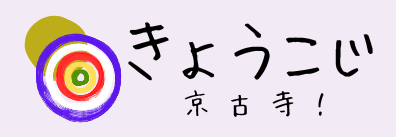京都古寺【毘沙門堂】
毘沙門堂の歴史
About History
毘沙門堂は「毘沙門堂門跡」とも呼ばれ、正式名称を「護法山 安国院 出雲寺(いずもじ)」といいます。

毘沙門堂はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

文武天皇の勅願により、大宝3年(703年)に行基が開いた「出雲寺」が始まりと伝わっています。
鎌倉時代初めの建久6年(1195年)に、平親範(たいらのちかのり)が平等寺と尊重寺の二寺を護法寺にまとめ(いずれも平家ゆかりの寺院)、出雲寺を継ぐ形で毘沙門天像を本尊とする精舎を建立しました。
応仁の乱等により焼失し一時は廃絶しましたが、徳川家康の側近であった南光坊天海が再興に着手。寛文5年(1665年)に天海の弟子・公海によって山科の地で再興されました。
※「毘沙門堂」と呼ばれたのはこの頃からだと言われています
その後、後西天皇の皇子・公弁法親王が入寺されたことにより門跡寺院(皇族や摂関家が住職となる寺院)となり、現在に至っています。
毘沙門堂の見どころ
Highlights
毘沙門堂にはいくつか見どころがありますが、ここでは次の3つ+1に厳選してご紹介いたします。

では、それぞれ詳しく見ていきますね!
不思議だなぁ~
「九老之間・襖絵」
毘沙門堂の拝観受付を済ませると、「本堂(本殿)」「霊殿」「宸殿」の3つのお堂を拝観することができます。
その中で、ぜひ見ていただきたいのが宸殿「九老之間」の襖絵。

こちらにある襖絵は、狩野探幽の養子・狩野益信により描かれたもので、「動く襖絵」として知られています。

堂内は写真撮影不可なので、残念ながらお見せすることができません
襖絵の前に置かれている解説には、襖絵を見ながら左右に歩いてみると、絵の中の机の向きや長さが変わるとのこと。
「そんなことないやろぉ~」と思いながらも、襖絵を見ながら右左移動しながら見ると、確かに机の長さや向きが変わる!
こちらの襖絵は「逆遠近法」という手法で書かれているそうで、その名の通り、通常の遠近法とは逆に(手前が小さく、奥が大きく)描かれているとのことです。
しかしなぜ逆遠近法だとこのように動いて見えるのかが私にはわからなかったです…

百聞は一見に如かず、ぜひ現地でご覧ください!
ちなみに、宸殿には九老之間の襖絵以外にも、円山応挙筆とされる「鯉の杉板戸」というものもあります。
こちらも、右から見た場合、正面から見た場合、左から見た場合で鯉の向きが変わる不思議な絵になっていますので、お忘れなく!
ほっと一息
「晩翠園」
宸殿を進んでいくと、「晩翠園(ばんすいえん)」というお庭に出てきます。


こちらは江戸時代初期に作庭されたもので、心字池を中心とした回遊式庭園になっています。
※ただ、宸殿から降りて散策することはできません
奥には、屋根の反り具合が美しい「観音堂」がポツンと建っています。

晩翠園では、春には躑躅(つつじ)、夏には百日紅(さるすべり)、秋から冬にかけては山茶花(さざんか)などの花々をご覧いただけます。

静寂の中で、ほのかに聴こえる滝の音に癒されます笑
毘沙門堂の代名詞!
「紅葉」
毘沙門堂の代名詞といったら、やはり「紅葉」ですね。


赤く染まった木々を見るのもいいですが、晩秋になると見られる、落ち葉で紅く染まった「敷き紅葉」も人気があります。


ちなみに、晩翠園の紅葉もお見事ですよ!

また、本殿の裏側から見える高台弁才天付近も撮影スポットとして人気があります。

紅葉は季節が限定されますが、ぜひ紅葉の季節に行ってみてはいかがでしょうか?
紅葉穴場スポット
塔頭「双林院」
毘沙門堂から徒歩2分ほどのところに「双林院」というところがあります。

こちらは毘沙門堂の塔頭(子院)で、「山科聖天(やましなしょうてん)」とも呼ばれています。

毘沙門堂の境内(宸殿近くの出入口)から行くこともできます
境内へは自由に入ることができ、境内に入ってすぎ右側にあるのが本堂「聖天堂」。

御本尊の「大聖歓喜天(秘仏)」の他、武田信玄から奉納されたといわれる歓喜天などが祀られています。

堂内はお線香なのか、ほのかに甘い香りがします笑
この他にも不動堂や阿弥陀堂があります。


ちなみに、不動堂に祀られているお不動さんは、織田信長の比叡山焼き討ちの際に損傷した仏像の部材を集めて造られたものと伝わっています。
実はこちらの双林院でも紅葉が見られ、「知る人ぞ知る、紅葉の穴場スポット」になっています。



毘沙門堂が混雑している場合は、こちらの双林院で紅葉をご覧になっても良いかもしれませんね!
ぐるっと毘沙門堂
Around Bishamondo
毘沙門堂の境内で、その他気になったものをいくつか取り上げておきます。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は30分くらいです
仁王門

毘沙門堂境内に入り、石段を登っていくとあります。その名の通り、阿吽の仁王像(江戸時代初期に造られたもの)が左右にいます。大きな「毘沙門天」と書かれた提灯が目印です。
本殿(本堂)

拝観受付を済ませ、目の前に見えるお堂です。徳川家の寄進により建てられました。御本尊は毘沙門天様ですが秘仏となっており、お前立の毘沙門天が見られます。
高台弁財天

本殿の斜め後ろにあります。こちらの高台弁才天は豊臣秀吉の母・大政所ゆかりの弁才天で、元は大阪城や高台寺に祀られた後、毘沙門堂へ移築されたそうです
般若桜

霊殿の前にある枝垂桜で、「毘沙門しだれ」や「一目千両」などとも呼ばれているそうです。樹齢は150年以上で、枝張り(枝の四方の長さ)が30mあるそうです。
勅使門

霊殿の前にある門で、毘沙門堂の正門になります。ただし、通常時は通れません。晩秋には、この勅使門前にある石段の「敷き紅葉」が撮影スポットとして人気を集めます。
御朱印

毘沙門堂の御朱印は拝観受付のところでいただけます。直書きと書置きがありますが、私は鮮やかな書置きにしていただきました。内容は、御本尊の「毘沙門天王」になります。
アクセスと拝観情報
Access & Information
毘沙門堂へは最寄駅から徒歩で行けます。
毘沙門堂の最寄り駅は、JR/地下鉄/京阪「山科」駅です。
駅の出口から線路に沿って東へ進むと小さな踏切がありますので、そこを左へ曲がります。
そのまま直進すると、毘沙門堂前まで到着します。
山科駅から毘沙門堂前まで徒歩約17分です。
| 拝観時間 | 【毘沙門堂】 9:00~17:00(3月~11月) 9:00~16:30(12月~2月末日) ※拝観受付は30分前まで ※御朱印受付は1時間前まで 【双林院(山科聖天)】 9:00~16:00 ※開門は8:00から |
| 拝観料 | 【境内】 無料 【本殿・霊殿・宸殿】 大人:700円 高校生・中学生:400円 小学生:300円 ※団体割引あり (15名以上) 【双林院(山科聖天)】 無料 |
| 所在地 | 京都市山科区安朱稲荷山町18 |
| TEL | 075-581-0328 |
| ホームページ | 【毘沙門堂】 https://www.bishamon.or.jp/ 【双林院(山科聖天)】 https://yamashina-syouten.com/ |
| その他 | 境内に無料駐車場有り ※ただし、桜・紅葉シーズンでは利用不可 |
ちょっとそこまで
Neighborhood
毘沙門堂の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください
安祥寺

毘沙門堂と同じく山科駅が最寄り駅で、駅からだと徒歩10分ほどで行けます。令和6年(2024年)に「五智遍明庭(ごちへんみょうてい)」というお庭が完成しました。ただし通常非公開で、毎月限られた日にちしか拝観できません。
本圀寺

地下鉄・京阪「山科」駅の1つ隣、「御陵(みささぎ)」駅が最寄り駅で、駅から徒歩13分ほどで行けます。以前は西本願寺の北側にありましたが、昭和44年(1969年)に現在地に移転しました。境内の枝垂桜が有名です。
毘沙門堂周辺地図

以上、毘沙門堂についてでした!
こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^
関連記事
Related Articles
奈良県平群町にある古寺です。毘沙門堂と同じく、毘沙門天王を御本尊とするお寺です。朝護孫子寺は日本で最初に毘沙門天王が現れたところと言われています。